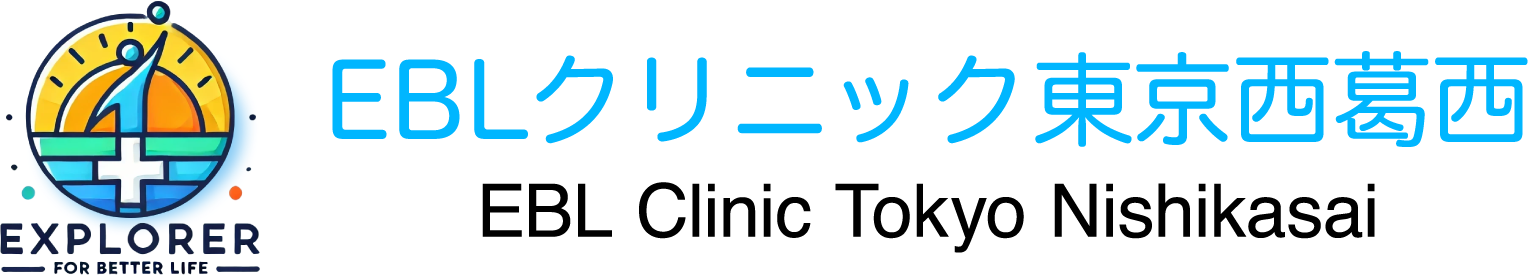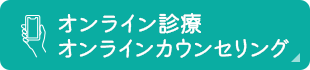認知症について
 認知症とは、何らかの原因で、記憶や思考などの認知機能が低下し、日常生活に様々な支障をきたす病気です。認知症には種類があり、「アルツハイマー型認知症」をはじめ「レビー小体型認知症」「血管性認知症」などがあります。認知症は種類や患者様によって、症状の現れ方が異なり、治療法も異なります。認知に関して気になる症状がありましたら、お早めにご相談ください。
認知症とは、何らかの原因で、記憶や思考などの認知機能が低下し、日常生活に様々な支障をきたす病気です。認知症には種類があり、「アルツハイマー型認知症」をはじめ「レビー小体型認知症」「血管性認知症」などがあります。認知症は種類や患者様によって、症状の現れ方が異なり、治療法も異なります。認知に関して気になる症状がありましたら、お早めにご相談ください。
痴呆とは
痴呆とは、認知症の以前の呼び方です。痴呆という言葉には、侮辱的な表現が含まれており、早期受診や早期発見の妨げにもなることから、2004年に厚生労働省によって呼称が変更されました。
軽度認知障害(MCI)
軽度認知障害(MCI)とは、日常生活に支障があるほどではないものの、記憶などの認知機能が若干低下している状態で、認知症の前駆的症状です。軽度認知障害になると、約40%の人が5年以内に認知症へと進行してしまうため、早期治療によって認知症への進行を食い止めることが重要です。軽度認知障害の疑いがある場合は、できるだけ早く受診するようにしましょう。
加齢による物忘れとの違いは?
加齢による物忘れと認知症との違いは、加齢による物忘れの場合は出来事の一部を忘れてしまうのに対して、認知症の場合は出来事があったこと自体を忘れてしまいます。他にも、物忘れが日常生活へ支障がある場合は認知症、支障がない場合は物忘れとして扱います。加齢による物忘れと認知症による物忘れの主な違いについては以下の表の通りです。
| 物忘れ | 認知症 | |
|---|---|---|
| 物忘れの自覚 | ある | ない |
| 出来事自体を覚えているか | 覚えているが一部が思いだせない | 覚えていない |
| 日常生活への影響 | ない | ある |
| 判断力 | 保たれている | 低下している |
認知症の原因
認知症の原因は、認知症の種類によってそれぞれ異なります。最も多いアルツハイマー型認知症の場合は、脳内で作られるアミロイドβたんぱく質が異常に蓄積することが原因とされています。また、レビー小体型認知症は、レビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質が脳に蓄積することが原因とされています。血管性認知症は、脳内の血管が詰まったり破れたりして起こる脳血管障害が原因となり発症します。
認知症の原因になる病気
慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、正常圧水頭症、ヘルペス脳炎、HIV脳症、ビタミンB1欠乏症、ビタミンB12欠乏症などの病気が認知症の原因となることがあります。
認知症の種類
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症とは、脳の中にアミロイドβなどの不要なたんぱく質が蓄積してしまうことで、神経細胞が障害されてしまい、脳の海馬や頭頂葉が萎縮することで、症状が起こる認知症です。アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も多い種類の認知症です。症状は、物忘れなどの「記憶障害」から始まり、次第に自分の居場所や現在の時間などがわからなくなる「見当識障害」、物を隠したり盗まれたと訴える「物盗られ妄想」、徘徊などの症状が現れます。
アルツハイマー型認知症の症状
アルツハイマー型認知症の代表的な初期症状は、物忘れです。アルツハイマー型認知症は初期段階で治療を開始することで、進行スピードを遅らせることができますが、このアルツハイマー型認知症による物忘れの症状は、加齢による物忘れと間違えられることが多いため、注意が必要です。会話していて、出来事や体験そのものを忘れていることが多かったり、続いたりする場合や、いつも行っていた料理や掃除などの作業の手順を忘れてしまっている、通いなれた道で迷子になったりする場合は、アルツハイマー型認知症が疑われるため、早めに受診しましょう。アルツハイマー型認知症になると、何度も同じ話を繰り返したり、物の名前が一致しなくなったりと、周りの人はストレスを感じてしまうこともありますが、否定せずに、本人が過ごしやすい環境を整えてあげることが重要です。
アルツハイマー型認知症の治療
アルツハイマー型認知症の根本的な治療法は、現時点では確立されていないため、主な治療は、認知症の悪化を食い止める治療となります。アルツハイマー型認知症の治療では、大きく分けて薬物療法と非薬物療法の2つがあります。薬物療法では、認知機能を改善する薬や、行動・心理症状を抑える薬を投与し、症状を軽減します。非薬物療法では、認知機能のリハビリや生活のリハビリとして、音楽を聴く、昔のことを回想する、園芸を行うなどの方法が推奨されています。また、患者様の健康状態もアルツハイマー型認知症に少なからず影響を与えるため、健康管理も治療のひとつとして重要です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症とは、脳の神経細胞にできるレビー小体というたんぱく質が蓄積し、神経細胞が破壊されることで、脳の命令が上手く伝達されなくなることで起こる認知症です。レビー小体型認知症の発病率は、男性の方が高く、女性より約2倍高いとされています。脳の後頭葉と呼ばれる視覚を司る部分にレビー小体が集中すると、現実にはないものが見えてしまう幻視の症状が出ます。「家の中に知らない人がいる」「服の中に虫が沢山入ってきた」のような現実にはないことを言い出すようだと、レビー小体型認知症が疑われます。なお、レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症と比べると海馬の萎縮は少ないことが多いです。
レビー小体型認知症の症状
レビー小体型認知症は初期症状として、物忘れよりも「幻視」が現れることが多いとされています。また、幻視のほかに、自分をまだ子どもであると思い込んだり、定年してから何年も経つのに自分はまだ働いていると思ったりするような「誤認妄想」が現れることも多いです。その他にも、手足が震えて動けなくなる「パーキンソン症状」や寝ているときに大声を出すなどの「睡眠障害」を発症することも多いです。幻視の症状が現れたときは、周りの人は否定せずに話を合わせてあげましょう。本人には見えているため、否定してしまうと、かえって混乱してしまい症状が悪化してしまう原因となることがあります。
レビー小体型認知症の治療
レビー小体型認知症の根本的な治療法は、現時点では確立されていないため、主な治療は症状に合わせた対症療法となります。レビー小体型認知症の治療では、アルツハイマー型認知症の治療と同じように、薬物療法と非薬物療法を並行して行います。非薬物療法では、幻視を減らすために、部屋の明るさを統一したり、レイアウトをシンプルにすることや、回想法、音楽療法などで気持ちを安定させます。また、レビー小体型認知症は転倒の危険性があるため、リハビリテーションによって、運動能力を保つことが重要です。
血管性認知症
血管性認知症とは、脳梗塞や脳卒中、くも膜下出血などの脳血管障害が原因となって起こる認知症です。前頭葉や頭頂葉、側頭葉、後頭葉、海馬などの脳の認知機能を司る部分で血管が詰まり、十分な酸素や栄養が送られなくなることで、細胞が死滅し、血管性認知症を発症します。脳の血管は、高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病によって詰まるため、血管性認知症を予防するには、日頃の生活習慣を見直すことが重要です。また、血管性認知症はアルツハイマー型認知症と同時に発症することも多く、その場合は「混合型認知症」と呼ばれます。
血管性認知症の症状
血管性認知症の症状は、主に「記憶障害」や「判断力障害」です。症状は、一日のうちに波があります。また、血管性認知症の症状として、感情のコントロールが効かなくなり、すぐに泣いたり怒ったりする「感情失禁」も多くの場合でみられます。他にも、手足の震えや麻痺といった「運動障害」や食べ物が上手く呑み込めない「嚥下障害」、尿や便が出せなかったり、漏らしてしまう「排泄障害」などが起こることもあります。血管性認知症の症状は、損傷した脳の部位によって異なります。身体機能が低下して寝たきりになってしまうこともあるため、リハビリなどを行って身体機能を維持することが重要です。
血管性認知症の治療
血管性認知症の治療は、原因となっている高血圧や糖尿病、脂質異常症などに対する薬物療法です。脳の細胞は一度死滅してしまうと戻ることはなく、脳血管性認知症は、脳血管障害の再発によって悪化していくため、薬物療法や、運動、禁酒、喫煙などの生活習慣の改善などの再発の予防を行うことが重要です。また、脳血管性認知症はアルツハイマー型認知症を合併することもあるため、その場合は、抗認知症薬が用いられます。その他にも、リハビリによって脳を活性化し、症状の進行を遅らせることができると考えられているため、理学療法士や作業療法士によるリハビリが行われます。理学療法士や作業療法士によるリハビリが必要な場合には、連携する医療機関を紹介します。
前頭側頭型認知症
前頭側頭型認知症とは、合わせて脳の約4割を占めている前頭葉と側頭葉が萎縮し、血液の流れが滞ることで発症する認知症です。前頭側頭型認知症の初期症状は、物忘れよりも、性格の変化や異常行動が現れることが多いです。性格の変化や異常行動は、思考や感情のコントロールを司る前頭葉と言葉の理解や聴覚、味覚を司る側頭葉が障害されているため起こります。
前頭側頭型認知症の症状
前頭側頭型認知症の進行は、「初期」「中期」「後期」の3つの段階にわかれ、それぞれの段階で症状の特徴があります。初期では、感情が麻痺し、ぼんやりしていることが増えたり、他者への興味がなくなります。また、身だしなみにこだわりがなくなったり、同じ行動を繰り返したり、万引きや痴漢を起こすこともあるため、これらの異常行動から精神疾患と間違われることもあります。中期では、同じ行動を繰り返す「常同行動」や集中力の低下が起こります。会話中に突然立ち去ることもあります。後期では、精神状態が不安定になり、食事が減り、部屋に引きこもったりします。前頭側頭型認知症の進行は緩やかで年単位で進行しますが、最終的には寝たきりになる可能性があります。
前頭側頭型認知症の治療
前頭側頭型認知症の根本的な治療法は、現時点では存在しないため、症状を和らげる対症療法が行われます。盗み癖などの異常行動に対しては鎮静作用のある薬を処方するなど、症状に合わせて薬物療法が行われます。
認知症の初期症状(前兆)
認知症の初期症状は、物忘れなどの「記憶障害」や、自分の居場所や現在の時間がわからなくなる「見当識障害」、ものごとの理解や善悪の判断ができなくなるといったものがあります。
物忘れ(記憶障害)
- 同じことを繰り返し話す
- 直近の出来事を忘れてしまう
- ご飯を食べたこと自体を忘れてしまう
- 家族や友人の名前が思い出せなくなる
- 同じ物を繰り返し買ってしまう
- 物を置いた場所や片づけた場所がわからなくなる
- いつも何かを探している
- 料理や洗濯などの家事、長年続けていた仕事などができなくなる
- 食事や入浴など日常の動作があいまいになる
- 約束した日にちを忘れてしまう、約束したこと自体を忘れてしまう
など
見当識の障害
- 今居る場所、現在の時間がわからなくなる
- 今日の日にちや曜日かがわからなくなる
- 毎日通っている道でも迷ってしまう
など
理解力・判断力の低下
- 家電やテレビの操作などの慣れているはずの操作ができない、ミスが多い
- 会話の理解ができにくい
- 現在の状況が理解できない
- 怒りっぽくなった
- 実際に起こっていないことを起こっていると思い込む(妄想・幻視)
など
認知症の治療
認知症は、現時点では根本的な治療法はありませんが、薬物療法やリハビリなどの適切なケアを行うことで、症状を軽くしたり、進行を遅くすることは可能です。
薬物療法による治療
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬とは、認知や記憶に関係する神経伝達物質のアセチルコリンを分解するコリンエステラーゼの働きを抑えることで、脳内のアセチルコリンを増やし、認知症の進行を遅らせることが期待できる薬です。
ドネペジル塩酸塩
ドネペジル塩酸塩とは、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬のひとつで、1日1回の服用で、軽症から重症の方まで効果があります。
ガランタミン
ガランタミンとは、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬のひとつで、1日2回の服用で、軽症から中等症の認知症に適応する薬です。
リバスチグミン
リバスチグミンとは、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬のひとつで、パッチ剤と呼ばれる経皮吸収型薬です。背中、上腕、胸のどこかの健康な皮膚に貼り付け、24時間で交換します。症状が進行して、薬の内服管理が難しい方でも使用することができます。
NMDA受容体拮抗薬
NMDA受容体拮抗薬とは、脳内のNMDA受容体に結合して遮断することで、過剰に分泌されたグルタミン酸によるNMDA受容体の異常な活性化を防ぎ、脳内の情報伝達物質を整え、記憶障害などの進行を抑える薬です。
メマンチン
メマンチンとは、NMDA受容体拮抗薬のひとつです。中等度から高度のアルツハイマー型認知症の治療に用いられます。アセチルコリンエステラーゼ阻害薬との併用が可能です。
レケンビR点滴静注
レケンビR点滴静注とは、NMDA受容体拮抗薬のひとつで、認知症の新薬として日本では2023年に承認された薬です。アルツハイマー型認知症の原因とされるアミロイドβに作用する世界初の薬で、アルツハイマー型認知症の進行を抑制し、認知機能や日常生活機能の低下を遅らせます。認知症の初期や、軽度認知障害(MCI)に効果が期待されています。
認知症の行動・心理症状(BPSD)の治療
認知症の行動・心理症状(BPSD)とは、妄想や暴言、性的逸脱行為、抑うつ、徘徊などの認知症の精神的、行動的な症状のことです。これらの症状は、カウンセリングや環境の調整、リハビリなどの心理療法を用いて改善を図ります。心理療法による改善効果が見られない場合は、抗うつ薬や抗精神病薬などを用いた薬物療法を行います。
認知症の対応のポイント
共感する
認知症の方を対応する際には、否定せず共感を示すことが重要です。認知症の症状の妄想や幻視は、本人にとっては本当のことを伝えているつもりであるため、否定してしまうと、本人はどんどんと自信を無くし、否定されるストレスから認知症の症状が悪化してしまうことがあります。認知症は記憶は残りにくく忘れやすいですが、感情はなくならないため、否定されたという感情は残ります。
自尊心を傷つけない
認知症の対応をする際には、自尊心を傷つけないようにすることが重要です。認知症によって起こる行動や発言を否定したり、赤ちゃん扱いなどをすると認知症の人は自尊心が傷つけられたと感じます。自尊心が傷つくと、自信を無くしたり、コミュニケーションが減ったり、うつなどの症状が現れることもあります。コミュニケーションを取る際には、本人のペースに合わせた対応を行い、自尊心を傷つけないようにしましょう。
距離を置くことも大切
認知症の症状が進行すると、介護者の負担は増える一方であるため、介護がつらいと感じたら、本人と距離を置くことも重要です。例えば、本人が混乱している中で説得することは困難であるため、介護者は一度本人の目の前から離れてみましょう。距離を取ることで、本人も介護者も気持ちが楽になることがあります。また、認知症は進行していくものなので、施設入居や介護サービスなどを利用するのも手段のひとつです。
若い人でも認知症になる?
高齢者に属する65歳以上にならないうちから、認知症を発症することもあります(若年性認知症)。若年性認知症は、多い方から脳血管性認知症、アルツハイマー型認知症、交通事故後遺症による認知症、アルコール性の認知症の順になります。若年性認知症の場合は、他の病気が原因となっている可能性が否定できないため、しっかりと検査を行う必要があります。当院では、若年性認知症が疑われる場合は、より専門的な検査を行うために連携する病院を紹介し、治療を行っています。