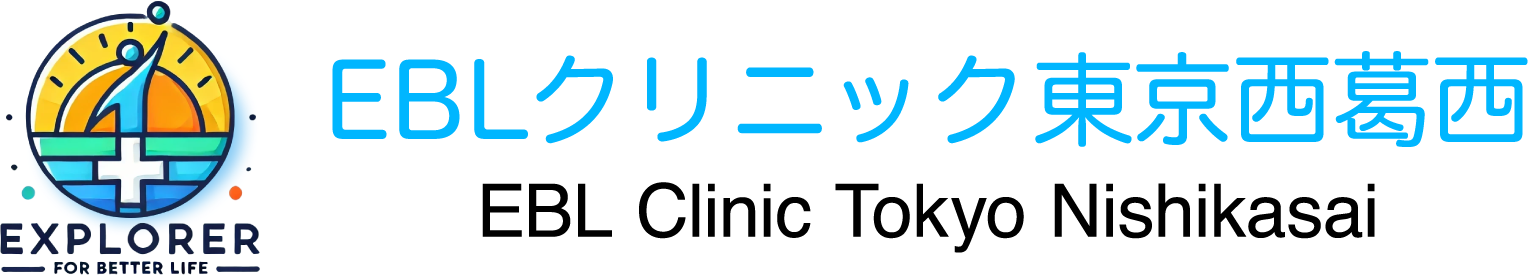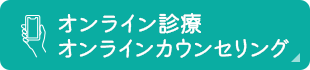HSPとは
 HSPとは、1996年にアメリカの心理学者エイレン・N・アーロンが提唱した、感受性が強く敏感で繊細な気質のことです。HSPは病気ではなく、その人がもっている心理的傾向で、繊細で刺激に敏感であることによって社会生活で生きづらさを抱えるという特徴があります。一方高い感受性により、芸術分野などで力を発揮することもあります。HSPは、生きづらさに対してただ我慢するのではなく、それぞれの対処法を見つけていくことが重要になります。なお、アーロン博士の調査によると、HSPは5人に1人程度の割合で存在しているとされています。
HSPとは、1996年にアメリカの心理学者エイレン・N・アーロンが提唱した、感受性が強く敏感で繊細な気質のことです。HSPは病気ではなく、その人がもっている心理的傾向で、繊細で刺激に敏感であることによって社会生活で生きづらさを抱えるという特徴があります。一方高い感受性により、芸術分野などで力を発揮することもあります。HSPは、生きづらさに対してただ我慢するのではなく、それぞれの対処法を見つけていくことが重要になります。なお、アーロン博士の調査によると、HSPは5人に1人程度の割合で存在しているとされています。
HSPとうつ病
HSPはうつ病の違いは、共通する特徴があるものの、HSPは生まれつきの気質であるのに対して、うつ病は後天的な脳内の神経伝達物質の異常によるということです。ただし、HSPの人は、社会的局面で繊細な感受性によって、自己肯定感を保つことに困難を抱えやすく、そのストレスによってうつ病を発症してしまうことがあります。HSPの傾向がある方は、在宅ワークができる仕事を選ぶなど、生きづらさを抱えにくい社会との関わり方を探してみるのも良いかもしれません。
HSS型HSP
HSS型HSPとは、「刺激追求型HSP」とも呼ばれる心理的傾向で、好奇心が旺盛で、新しいことに挑戦したり、スリルを求めて大胆な行動をとったり、マルチタスクやリーダーシップを発揮するのも得意であるものの、感受性が繊細であるため、あとから疲れてしまったり、裏で疲れて傷ついたりしてしまうHSPのタイプです。
HSPの特徴
HSPの気質には以下のような特徴があります。
深く情報を処理する
HSPの人は、人よりも深く情報を処理することができるため、場の雰囲気や空気を読むことが得意です。その反面、情報を多く取り入れてしまうため、疲れてしまいます。
過剰な刺激を受けやすい
HSPの人は、光や音、味やにおい、気候の変化、人が発している目に見えないエネルギーなどの外部からの刺激に敏感です。これらの刺激に過敏に反応してしまいます。
共感しやすい
HSPの人は、周りの人の感情を読み取って共感しやすかったり、自分を重ねて考えてしまったりするため、小説や漫画、アニメ、ドラマ作品などの登場人物に強く感情移入してしまいます。
心の境界線が薄い・もろい
HSPの人は、他者との心の境界線が人よりももろいため、他者の影響を受けやすいという特徴があります。また、共感しやすいという特徴もあるため、人の感情に引きずられやすく、自分を見失ってしまうことも多いです。
疲れやすい
HSPの人は、他者に対して敏感であるため、楽しいことも嫌なこともつらいことも、人よりも強く感じられて、疲れやすいです。これは、何かしらの行動をしているときに限らず、無意識のうちに常にセンサーを張り巡らせているため、自動的に周りからの様々な情報を受けてしまい、疲れてしまいます。
自己否定が強い
HSPの人は、繊細な感覚によって、対人関係においても必要以上に自分の責任を強く感じすぎてしまい、自己肯定感が保てず、自信をもって行動できなかったり、落ち込んでしまったり、自己否定をしてしまうことがあります。
HSPへの向き合い方
HSPは、もって生まれた気質であるため、それを理解し受け入れることが楽に生きていくためには重要です。また、つらい思いをする場面も多いですが、状況によっては優れた力を発揮できる面もあります。自分の特性を受け入れるためのポイントは以下のようなことが挙げられます。
自分を客観的に見る
自分の特性を受け入れるためには、自分がどのような場面でつらさを感じ、どのような場面でリラックスできるのかを理解することが重要です。そのために、客観的な記録として、場面と状態や感情などをノートやスマートフォンなどに記録しておくことが役に立ちます。HSPの人は、自分を客観的に見ることが苦手な傾向があるため、このような記録を残すことは自分を理解するために有効です。
外の環境からの刺激を上手に和らげる
HSPの人は、外からの刺激に敏感であるため、音に対しては耳栓やノイズキャンセリングイヤホンを装着する、光に対してはサングラスを身に着けるなどの、外からの刺激に対する対処法を用意しておくことが重要です。手元にあるものなどをできるだけ活用しながら、刺激に対するバリアを用意していきましょう。
緊張しにくい環境に身をおく
HSPの人は、強い感受性によって緊張しやすく、人といると、自分がどう思われているかが常に気になってしまったり、失敗を恐れて集中できなくなってしまったりします。そのため、仕事は在宅ワークができるものを選んだりなど自分が安心してリラックスできる環境を整えることで、緊張感を軽減することができます。
HSPセルフチェック
自分がHSPの傾向にあるかどうかを、ある程度確認することができます。以下の質問に少しでも当てはまる場合はご相談ください。
- 他者の気分につられてしまうことが多い
- 自分がいる環境の些細な変化にすぐ気がつく
- 痛みには敏感で弱い
- 仕事などで忙しい時期が続くと、刺激が少なくプライバシーが守られるような場所に隠れたくなる
- カフェインに敏感で、カフェインがすこしでも入っているとすぐに気がつく
- 強い光、臭い、大きな音や、特定の肌触りなどがつらい
- 空想にふけるくせがある、想像力が豊か
- 音がうるさいと落ち着くことができない
- 芸術に感動する性質である
- ちょっとしたことにびっくりする
- 自分は良心的すぎるかもしれないと感じる
- 同時に多数のことを行おうとすると、パニックになってしまう
- 人が不快感を感じるポイントにすぐ気がつき、問題点を解決できる
- 一度に多くのことを依頼されるのが嫌い
- 失敗や忘れ物などが無いよう、いつも心を配っている
- 暴力的な場面が嫌いで、そのようなドラマや映画はなるべく観ない
- 周囲で複数のできごとが重なってしまうと気分が悪くなる、緊張してしまう
- 空腹であると、集中できない、機嫌が悪くなる、気分が悪くなる
- 香りや味などのデリケートな変化にもすぐ気がつく
- デリケートな音や音楽が好き
- いつもの生活に変化がおきると混乱してしまう
- 日常生活を乱すような状況を避けるためにいつも心を配っている
- だれかと競争するような場面や、観察されるような場面が苦手で緊張してしまう、いつもの力が発揮できない
- 子どものころから、周りの大人に、あの子は繊細だ、内気だと思われていた
以上の質問のうち、12個以上の質問にチェックがついた場合は、HSPの気質だと考えてよいでしょう。また、チェックの数が多いほど、HSPの度合いが高いと考えられます。一方、チェックが1つか2つであっても、強く当てはまる場合は、HSPと判断されることがあります。
HSPのよくある質問
HSPを治すことは可能ですか?
HSPは持って生まれた性格であり、気質です。そのため根本的な治療方法というのはありません。しかし、生きづらさの度合いが強くてお悩みの場合は、精神科や心療内科に相談してみると、カウンセリングなどによって、考え方の変化のきっかけを掴めることがあるかもしれません。
HSPに対する薬物療法はありませんか?
HSPは性格であり気質ですので、薬をつかっても治すことはできません。しかし、HSPからうつ病を発症したような場合には、抗うつ薬などで対応することはできます。ただしHSPの性格までは薬では治りません。