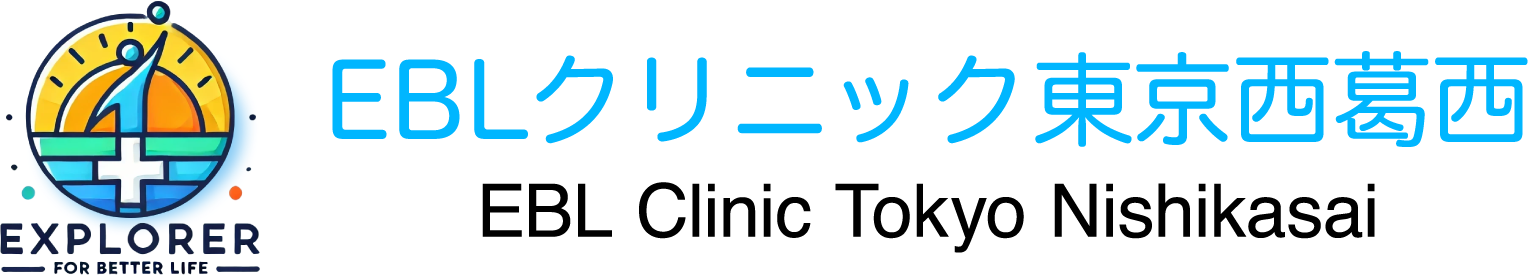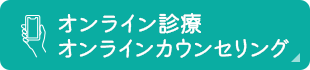睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まる、または弱くなる状態を繰り返す病気です。無呼吸とは、10秒以上呼吸が停止する状態を指し、これが7時間以上の睡眠中に30回以上、または1時間あたり5回以上見られる場合、睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されます。
この症状が続くと、酸素不足が繰り返されることで心臓病や脳卒中などの重大な健康リスクが高まります。また、慢性的な睡眠不足を引き起こし、日中の強い眠気や集中力の低下など、生活に支障をきたす可能性もあります。
睡眠時無呼吸症候群の原因・種類
睡眠時無呼吸症候群の主な原因は、気道が塞がる「閉塞性」のものが多いですが、呼吸中枢に問題が生じることで発症する「中枢性」のケースもあります。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群
閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、肥満、扁桃肥大、アデノイド肥大、顎の形状、舌が気道に落ち込む状態、鼻炎、鼻中隔湾曲症などが原因として挙げられます。これらの要因が睡眠中に気道を塞ぐことで無呼吸状態が引き起こされます。睡眠時無呼吸症候群の多くは、この「閉塞性」に分類されます。
中枢性睡眠時無呼吸症候群
一方、中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳内にある呼吸中枢が正常に機能しなくなることで発症します。このタイプでは、気道の閉塞が原因ではないため、閉塞性で見られるようなあえぐようないびきは伴いません。心不全、脳卒中、腎不全などの病気に伴って発症するケースが多いとされています。
睡眠時無呼吸症候群の症状
睡眠中
- 大きないびきをかく
- 息が止まっていると周囲に指摘される
- 自分のいびきで目が覚める
- 息苦しさを感じて目が覚める
- むせたり咳き込んだりして目を覚ます
- 夜中に頻繁にトイレに起きる
- 暑くないのに寝汗をかく
起床時
- 朝起きたときに頭痛がある
- 眠りが浅く、十分に寝ても疲労感が残る
- 起床後に倦怠感を感じる
- 目覚めが悪く、二度寝してしまう
日中
- 抑えられないほどの強い眠気がある
- 十分な睡眠時間を確保しても眠気が抜けない
- 集中力が低下し、些細なミスが増える
- 慢性的に疲労感を抱えている
- 瞬間的に意識を失うように眠ってしまうことがある
睡眠時無呼吸症候群の合併症
高血圧
 睡眠時無呼吸症候群は、高血圧を引き起こす原因の一つとされています。睡眠中に呼吸が止まるたびに血中の酸素濃度が低下し、交感神経が活性化することで血圧が上昇します。この状態が繰り返されると、血管に負担がかかり、高血圧が慢性化します。また、高血圧を放置すると、心疾患や脳卒中のリスクがさらに高まるため、早期の治療が重要です。
睡眠時無呼吸症候群は、高血圧を引き起こす原因の一つとされています。睡眠中に呼吸が止まるたびに血中の酸素濃度が低下し、交感神経が活性化することで血圧が上昇します。この状態が繰り返されると、血管に負担がかかり、高血圧が慢性化します。また、高血圧を放置すると、心疾患や脳卒中のリスクがさらに高まるため、早期の治療が重要です。
心疾患
 睡眠時無呼吸症候群は、心不全や狭心症、不整脈などの心疾患のリスクを高めます。無呼吸による酸素不足と交感神経の過剰な刺激が、心臓に大きな負担をかけるためです。特に心房細動などの不整脈は、無呼吸症候群と密接に関連していることが確認されており、未治療の場合、症状が悪化する可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群は、心不全や狭心症、不整脈などの心疾患のリスクを高めます。無呼吸による酸素不足と交感神経の過剰な刺激が、心臓に大きな負担をかけるためです。特に心房細動などの不整脈は、無呼吸症候群と密接に関連していることが確認されており、未治療の場合、症状が悪化する可能性があります。
脳卒中
無呼吸症候群は脳卒中の発症リスクを高める要因の一つです。酸素不足により血液がドロドロになり、血栓ができやすくなることや、血圧の変動が脳の血管に負担をかけることが主な原因です。特に閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者様は、脳梗塞や脳出血のリスクが高いと報告されています。
糖尿病
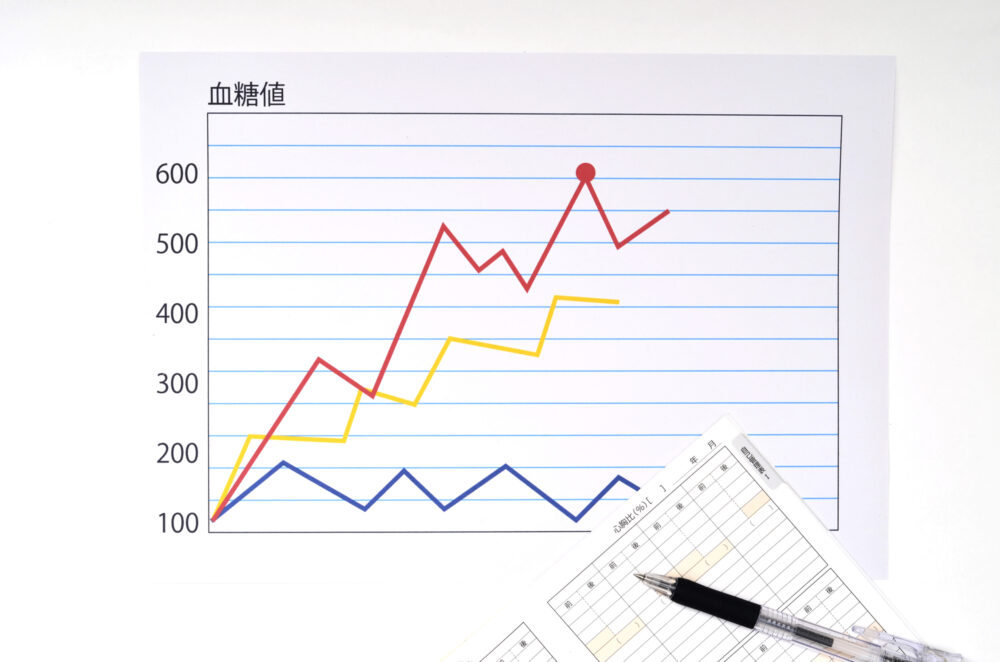 睡眠時無呼吸症候群は、2型糖尿病の発症や悪化とも関連があります。無呼吸による酸素不足や睡眠不足が、血糖値を調整するインスリンの働きを低下させるためです。また、睡眠不足が慢性化すると、インスリン抵抗性が高まり、糖代謝が悪化することが知られています。
睡眠時無呼吸症候群は、2型糖尿病の発症や悪化とも関連があります。無呼吸による酸素不足や睡眠不足が、血糖値を調整するインスリンの働きを低下させるためです。また、睡眠不足が慢性化すると、インスリン抵抗性が高まり、糖代謝が悪化することが知られています。
認知症
無呼吸症候群は、認知症や軽度認知障害(MCI)のリスクを高める可能性があります。夜間の低酸素状態が、脳細胞のダメージや記憶力の低下を引き起こすと考えられています。また、睡眠の質が低下することで、脳内の老廃物の排出が不十分になり、アルツハイマー型認知症との関連が示唆されています。
うつ病
睡眠の質が低下することで、うつ病の発症リスクが増加します。無呼吸症候群の患者様は、慢性的な疲労感や集中力の低下により、気分が落ち込みやすくなる傾向があります。また、質の良い睡眠がとれないことで、脳内の神経伝達物質バランスが崩れ、うつ症状が進行する可能性があります。
睡眠障害の検査・診断
簡易PSG検査
簡易PSG検査とは、携帯型の装置を就寝時に装着し、睡眠中の呼吸状態や心拍数、血中酸素飽和量を測ることで、睡眠状態を的確に調べる検査です。自宅で行うことが可能です。当院では、簡易PSG検査を常備しているため、お気軽にご相談ください。
ポリソムノグラフィー検査 (PSG)
ポリソムノグラフィー(PSG)検査とは、睡眠中の呼吸と血中酸素飽和量の計測に加え、脳波や眼球運動、呼吸運動、心電図、いびき、口と鼻の気流、睡眠時の姿勢なども計測することができる睡眠の精密検査です。検査が必要と思われた場合は、当院で実施します。
睡眠障害の治療
睡眠障害の治療では、まずは生活習慣の改善を行い、その上で必要に応じて薬物療法を行います。また、重症の睡眠時無呼吸症候群の場合は、CPAPという機械を用いた治療を行います。
CPAP
CPAP療法とは、睡眠中に専用のマスクを装着し、陽圧をかけた空気を気道に送り込むことで、気道を確保し、無呼吸や低呼吸を抑制する治療法です。専用の機器をご自宅に導入し、ご自身で機器を装着して就寝していただきます。CPAP療法は、改善効果が高く、ご自身で行えるため、現在は睡眠時無呼吸症候群の主な治療法となっています。しかし、CPAP療法は、対症療法であるため、治療を止めてしまうと、無呼吸や低呼吸が再発します。
薬物療法
 薬物療法では、睡眠障害に応じて、GABA受動態作動薬やメラトニン受容体作動薬など様々な薬を選択して処方します。薬には副作用を伴うものもあるため、医師の指示に従い服用しましょう。
薬物療法では、睡眠障害に応じて、GABA受動態作動薬やメラトニン受容体作動薬など様々な薬を選択して処方します。薬には副作用を伴うものもあるため、医師の指示に従い服用しましょう。