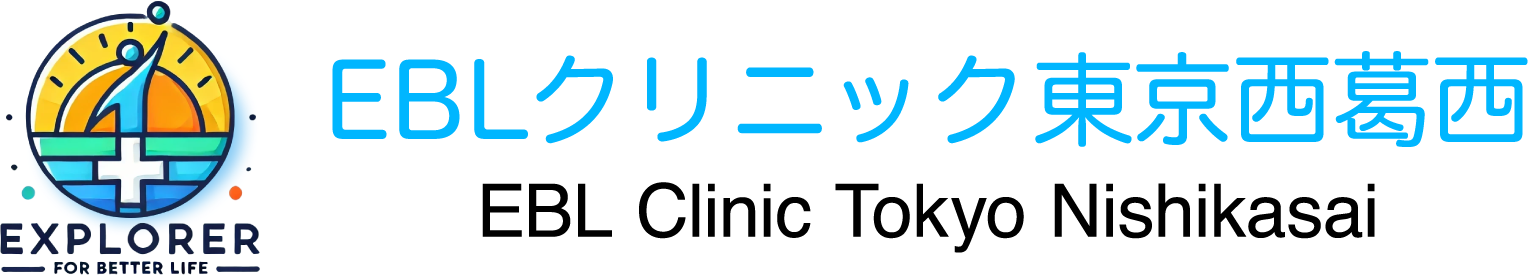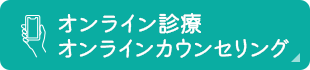- 適応障害とは
- 適応障害の原因
- 適応障害の症状
- 「適応障害」と「死別反応」
- 「適応障害」と「うつ病」
- 適応障害の検査・診断
- 適応障害の治療
- 適応障害かも?顔つきの変化
- 適応障害の人に向いている仕事
- 適応障害のセルフチェック
適応障害とは
 適応障害とは、その人にとって耐えがたいほどの強いストレスをうけて、そのストレスに適応できないことで、日常生活に支障をきたすような症状が現れている状態です。適応障害は、ストレスの対象がはっきりとしていることが特徴で、ストレスとなっている要因から離れて休養を取ることで、回復します。
適応障害とは、その人にとって耐えがたいほどの強いストレスをうけて、そのストレスに適応できないことで、日常生活に支障をきたすような症状が現れている状態です。適応障害は、ストレスの対象がはっきりとしていることが特徴で、ストレスとなっている要因から離れて休養を取ることで、回復します。
適応障害の原因
適応障害の原因は、耐えきれないほどの強いストレスです。原因となるストレスは、人によって異なりますが、引っ越しや就職、転職、転校、クラス替え、人事異動、昇進などが多いです。
適応障害の症状
- 1つことにこだわって考えすぎてしまう
- 感情のコントロールができなくなる
- 集中力が維持できなくなる、ミスがふえる
- 暴飲暴食してしまう
- 休みの日になると気分が楽になる
- 遅刻を繰り返す、無断欠席を繰り返す
- 衝動的に物にあたってしまう
など
「適応障害」と「死別反応」
適応障害の原因となるストレス要因は様々なものがありますが、死別が原因の場合は、適応障害とは診断されません。大切な人を無くした場合の強いストレスや行動の変化は、通常の反応であるとされていることが理由です。
「適応障害」と「うつ病」
適応障害とうつ病は、症状に共通するものがあるため、混同されてしまうことが多いですが、適応障害はストレスそのものが原因となって症状が起こるのに対し、うつ病はストレスによって脳の神経伝達物質のバランスに異常が起こることで症状が現れます。また、適応障害は、ストレス要因を取り除いたり、ストレス要因と距離を置くことで、症状が軽減するのに対し、うつ病は、ストレス要因を取り除いても症状は軽減されず、継続します。診断の際には、適応障害とうつ病の違いに注目して診断を行い、治療についても、適応障害の場合は、ストレス要因を取り除いたり低減したりするのに対して、うつ病の場合は、まずは脳の機能を正常に戻すことを目的とした治療を行います。
適応障害の検査・診断
適応障害は、以下の4つの基準をもとに診断を行います。
- ストレスの原因が明確かつ、ストレスを感じてから3ヵ月以内に症状が出ている
- ストレスにより強い苦痛を感じている、または生活に支障が出ている
- その他の精神疾患や、死別反応(大切な人を亡くした喪失感)ではない
- ストレスの原因がなくなると改善し、6ヵ月以内に症状が回復する
適応障害はストレスの原因が明確で、原因を遠ざけると症状が回復するのが特徴です。「原因は不明だが、こころや身体がしんどい」という方は、適応障害ではなく、他の病気の可能性が高いです。
適応障害の治療
適応障害の治療は、ストレスの要因を取り除いたり軽減することを目的とした環境調整と休養です。たとえばしばらくの間休職したり休学したりすることなどが必要な場合があります。また、これらのほかに薬物療法や心理療法を行うことがあります。
休職
ストレス要因によっては一定期間仕事から離れ、自宅で休養をとることで症状の改善を図ります。数日や1週間程度の休みではなく、1ヵ月単位のまとまった休みが必要です。当院では、1~2ヵ月程度の休養をお勧めし、その後は患者様と相談しながら、必要に応じて休職期間を調整していきます。休職はリワークプログラムを活用することで、スムーズな復職が期待できます。
異動などの環境調整
会社員である場合は、ストレス要因によっては、人事異動や配属先の変更、役職の変更など、働く環境の調整を行うことで症状が良くなることがあります。必要であれば、部署や配置を変更することが望ましいという旨を診断書に記載することも可能です。また、休職後に職場にこのような対応を依頼することもあります。ただし、異動については会社の規模や会社の考え方にもよるため、必ずしもできるものではありません。
退職・転職
ストレス要因によっては、退職や転職によって職場環境を変えることがあります。しかし、状態が悪いときや抑うつ状態が激しいときは、このような決定は急がないことが重要です。一度休職などの措置をとり、その上で家族や医師と相談して、時間をかけて今後の方針を決めると良いでしょう。
薬物療法
 不安や不眠には抗不安薬、うつ状態には抗うつ薬を使います。しかし、適応障害の薬物療法は、対症療法となるため根本的な治療ではありません。環境の調整なども含めて総合的に治療を進める必要があります。
不安や不眠には抗不安薬、うつ状態には抗うつ薬を使います。しかし、適応障害の薬物療法は、対症療法となるため根本的な治療ではありません。環境の調整なども含めて総合的に治療を進める必要があります。
心理療法
 当院では、認知行動療法を中心とした心理療法を行っています。考え方や捉え方に癖があったり、過度に自分を責めてしまいがちな方は、カウンセリングを受けることで多方面から物事を見ることができるようになります。
当院では、認知行動療法を中心とした心理療法を行っています。考え方や捉え方に癖があったり、過度に自分を責めてしまいがちな方は、カウンセリングを受けることで多方面から物事を見ることができるようになります。
適応障害かも?顔つきの変化
適応障害になると、抑うつや無気力感によって、目の下にクマが出来たり、顔色が悪くなったり、緊張した表情をしているなど、顔つきが変わることがあります。また、会話をしていても無表情が続いたり、上の空だったりと、コミュニケーションに変化が現れることもあります。
適応障害の人に向いている仕事
適応障害の症状がある間は無理に仕事をすることはお勧めできません。心身の健康第一に無理せずできそうな仕事につくことを考えましょう。適応障害の診断が出ている間は、仕事のリハビリもかねて、ハローワークに相談することも一つの手段です。
毎日やることが決まっている同じ仕事
軽作業や日課の決まっているような仕事は、毎日のやることが決まっていて、ストレスがかかりにくいため、適応障害の人に向いているかもしれません。
職場に馴染む必要がない仕事・一人でもできる仕事
エンジニアやクリエイター、芸術、ものづくりなど、他者とのコミュニケーションを取る必要がないような仕事は、人間関係のストレスを受けにくいという特徴があります。
在宅勤務が可能な仕事
パソコンや通信機器を利用した在宅ワークはたくさんあります。サイドビジネスや、それだけで自立した生活を営む人も近年増えています。
適応障害のセルフチェック
- 平日は気分が沈んでつらいが、休日は気持が軽い
- ちょっとしたことで、ついイライラしてしまう。引っかかってしまう。
- なかなか眠ることができない
- 体調を崩してしまいやすく、一度体調を崩すとなかなか治らない
- 動悸が激しい、息苦しい、胸が苦しい感じがする
- ちゃんと休みをとっているのに、疲れがとれない、疲れやすい
- 人間関係が面倒になってしまうことが多い
- 手足が冷えている
- 肩こり、首こりなどが続き、眠ることができない日もある
- めまい、ふらつき、立ちくらみ、吐き気などを感じる