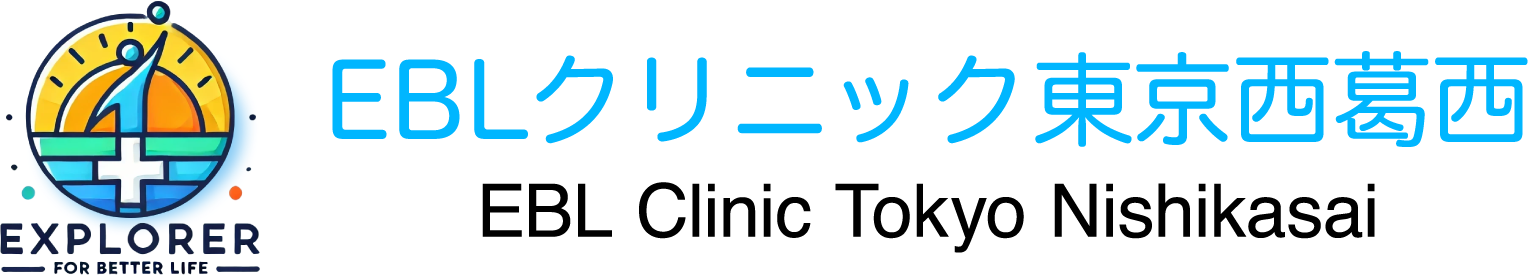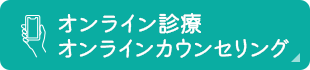統合失調症とは
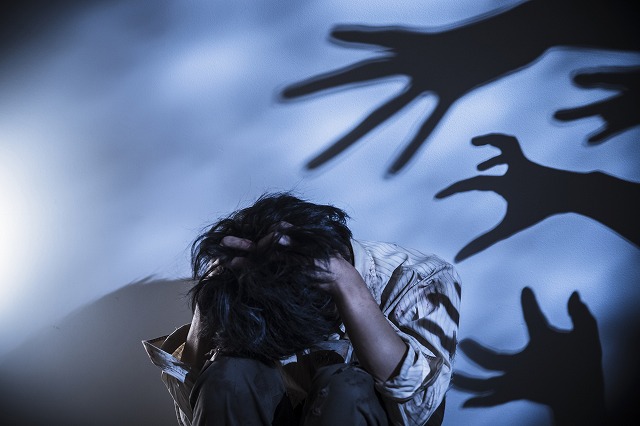 統合失調症とは、脳の働きの誤作動によって、認知や感覚といった脳の機能をまとめることができなくなってしまい、意欲低下や感情の平板化、幻覚、妄想、異常な思考や行動などの様々な症状が起こる病気です。思春期頃~40歳頃にかけて発症することが多いですが、稀に中年期以降にも発症することがあります。100人に1人程度が統合失調症を発症しているという頻度の病気です。症状は突然現れて、回復期にかけてゆっくりと病状は落ち着いていきますが、再発しやすいという傾向があります。そのため、病状を安定させるとともに、再発を防止のするための治療を続けていくことが重要です。
統合失調症とは、脳の働きの誤作動によって、認知や感覚といった脳の機能をまとめることができなくなってしまい、意欲低下や感情の平板化、幻覚、妄想、異常な思考や行動などの様々な症状が起こる病気です。思春期頃~40歳頃にかけて発症することが多いですが、稀に中年期以降にも発症することがあります。100人に1人程度が統合失調症を発症しているという頻度の病気です。症状は突然現れて、回復期にかけてゆっくりと病状は落ち着いていきますが、再発しやすいという傾向があります。そのため、病状を安定させるとともに、再発を防止のするための治療を続けていくことが重要です。
統合失調症の原因
統合失調症の原因は、明らかになっていませんが、遺伝的な要因にストレスなどが加わることで発症するのではないかと考えられています。また、近年の研究では、脳の伝達系の異常が関係していると考えられています。
神経伝達物質の異常
統合失調症になると、脳内の情報伝達物質のドーパミンが過剰に分泌され、その結果、幻覚や妄想といった症状を引き起こすとされています。その他にもセロトニンやGABA、グルタミン酸などの情報伝達物質も発症に関係しているとされています。
脳の機能障害、構造異常
統合失調症の人の脳をCT検査やMRI検査で確認すると、前頭葉や側頭葉といった脳の部位が、通常よりも小さくなっていることが観察されます。前頭葉や側頭葉が小さくなっていることと、統合失調症にどのような関係があるのかは明らかになっていませんが、脳の機能異常や構造異常が統合失調症の発症に関与しているのではないかと考えられています。
統合失調症の分類
統合失調症は、「妄想型」「破瓜型(はか型)」「緊張型」の3つの型に分けられます。
妄想型
妄想型は、主に妄想や幻覚などの症状があり、その他の症状はほとんどないことが特徴です。統合失調症の3つの型の中では特に症状が軽く、周囲の人からは病気であると認識されないこともあります。30歳前後の成人期に発症することが多い型です。
破瓜型(はか型)
破瓜型は、主に感情の平板化や支離滅裂な会話・行動などの症状があり、人格が解体してしまったと感じるような症状が現れます。統合失調症の3つの型の中では、最も罹患率が高い型です。10代から20代という比較的若い世代に発症することが多いです。
緊張型
緊張型は、激しい興奮状態と、昏迷・昏睡といった両極端の状態を繰り返します。突然動き回り奇声を発したかと思えば、じっと動かなくなったり、身体が緊張しすぎて不思議な姿勢のまま動かなくなってしまったりします。治療を一定期間続けることで症状は改善しますが、再発しやすいため注意が必要です。
統合失調症の症状
統合失調症の症状は、「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分かれます。
陽性症状
陽性症状とは、幻覚や妄想、思考障害などを中心とした症状です。主に以下のような症状が挙げられます。
- 会話に一貫性がない
- 他者の目には見えない何かが見える
- テレビ、ネットなどや超能力的なもので誰かが自分の悪口を言っていると主張する
- ずっと誰かに監視されていると感じる
- 誰かにだまされていると思い込む
- 会話の途中で突然言葉が出なくなり、会話が中断する
- 相手がいないのに挨拶やおじぎなどの身振りを繰り返す
- 興奮し、大声をだす
- 意味のない身体の動きを繰り返す
など
陰性症状
陰性症状とは、感情の平板化や意欲の低下、自閉などの症状です。思考も乏しくなります。
- 感情が平板になるにつれて、表情が乏しくなる
- 仕事や学業、日常生活などの意欲が低下する
- コミュニケーションをとることが難しくなる
- 一日中頭がぼーっとする
など
認知機能障害
認知機能障害とは、記憶力や集中力判断力に関する障害のことです。主に以下のような症状が現れます。
- 記憶力が低下する
- 集中力が低下し、注意が散漫になる
- 作業の段取りや作業の準備ができない
- ものごとを判断できなくなる、判断が難しくなる
など
統合失調症になりやすい人の特徴
統合失調症の原因やメカニズムは、未だ明らかにはなっていませんが、遺伝や脳の構造的問題、気質などに対してストレスが原因となることで発症すると考えられています。
統合失調症の診断
統合失調症の診断では、統合失調症が疑われる場合に、患者様だけでなく、ご家族などにも問診を行い、いつ頃からどのように症状が現れ始めたのか、病状の変化、日常生活における支障などについて把握します。その後、アメリカ精神医学会が作成した診断基準のDSM-5に基づいて診断を行います。
統合失調症の治療
統合失調症の治療では、薬物療法を中心に症状を抑えながら、心理療法を行い、社会復帰を目指していきます。なお、統合失調症は症状が消えても再発しやすいという特徴があるため、症状が治まった段階でも継続的に投薬を行っていきます。
薬物療法
統合失調症の陽性症状は、脳の神経伝達物質の1つであるドーパミンの分泌が過剰になっていることで引き起こされていると考えられているため、薬物療法では、抗精神病薬を用いて治療を行います。また抗精神病薬以外にも補助的に、睡眠薬や抗不安薬、抗うつ薬、気分安定薬、抗コリン薬、パーキンソン病の薬などを複合的に使用することがあります。
抗精神病薬
抗精神病薬を用いて、ドーパミンの受容体を遮断することで陽性症状を抑えます。また、単一の抗精神病薬だけでは症状がコントロールできないことがあるため、状態に応じて複数の種類の抗精神病薬を組み合わせることもあります。抗精神病薬は症状のコントロール以外にも再発防止効果が期待できるため、症状が治まったからといって自己判断で薬の服用をやめずに、医師の指示に従って服用を続けましょう。
SDA(セロトニン・ドーパミン拮抗薬)
SDR(セロトニン・ドーパミン拮抗薬)とは、神経細胞側の受容体を遮断することによって、ロトニンやドーパミンの働きをブロックする薬です。ドーパミンのコントロールによって陽性症状を緩和し、セロトニンのコントロールによって陰性症状を緩和します。主な薬には、リスペリドン、インヴェガ、ペロスピロン塩酸塩、ブロナンセリン、ラツーダなどがあります。
MARTA(多元受容体作用抗精神病薬)
MARTA(多元受容体作用抗精神病薬)とは、セロトニンやドーパミンだけではなく、ヒスタミンやアドレナリンなどの受容体をブロックする薬で、陽性症状、陰性症状の双方を改善する効果があります。主な薬には、ジプレキサ、シクレスト、クエチアピンなどがあります。
DSS(ドーパミン部分作動薬)
DSS(ドパミン部分作動薬)とは、ドーパミンが過剰な際には、ドーパミンの受容体を遮断し、ドーパミンが不足しているときはドーパミンの受容体を活性化する薬で、陽性症状、陰性症状の双方を改善する効果があります。主な薬には、アリピプラゾール、レキサルティなどがあります。
定型抗精神病薬
定型抗精神病薬とは、ドーパミンそのものの働きをブロックすることで、陽性症状を改善する薬です。しかし、ドーパミンをブロックすることで陰性症状が悪化する、副作用が大きい薬です。主な薬にはハロペリドール、スルピリド、クロルプロマジン塩酸塩、レボメプロナジンなどがあります。
心理療法
統合失調症の人は、幻覚や妄想といった症状への不安や、つらさ、苦しみなどを抱えているため、医師がカウンセリングによりこれらの症状との付き合い方をアドバイスしたり、心理療法を行います。
統合失調症チェックリスト
- 自分を責め立てたり、何かを命じたりするような声が頭の中で聞こえてくる
- 自分が誰かに操られているように感じる
- 知らない人が自分の悪口を言っており、嫌がらせをしてくるように思う
- 自分の考えていることが人に見透かされているように感じる
- 誰かに監視されていると感じる
- 激しい緊張と不安を感じる
- 楽しみ、嬉しさ、心地よさといった感覚が感じられなくなった
- 独り言を言うことが増え、一人笑いをする
- 会話することが苦痛になり、人と話さなくなった
- 頭の中がうるさくて眠れない
- 眠りすぎてしまう
- 混乱して、考えをまとめることができない
- 直前におきたことを思い出すことができない
- ちょっとしたことにも過敏になり、興奮したり、興味を削がれたりする
- 自室に引きこもって、一日中ぼんやりしていることが多い
- 何事にも気力や意欲が出ない、行動が億劫になる
- 即時に判断することができなくなった
- 一つのことに集中できなくなった